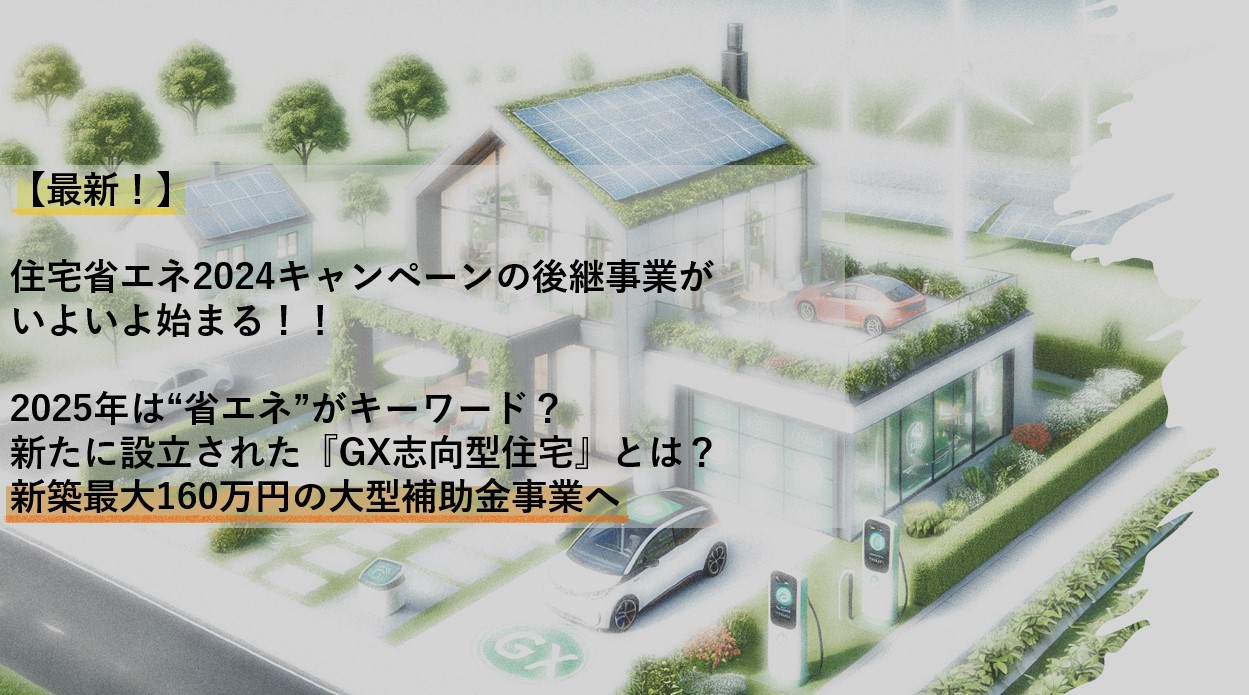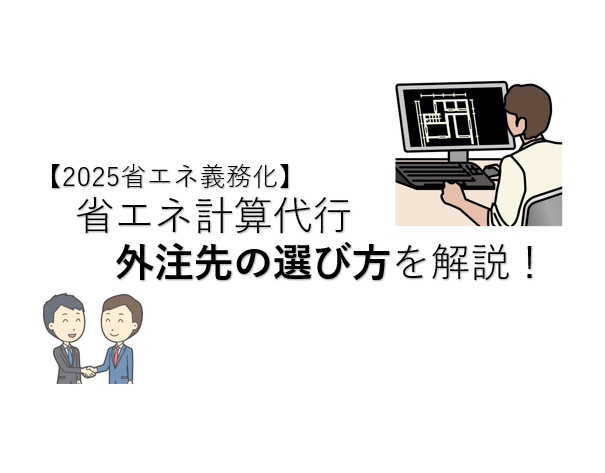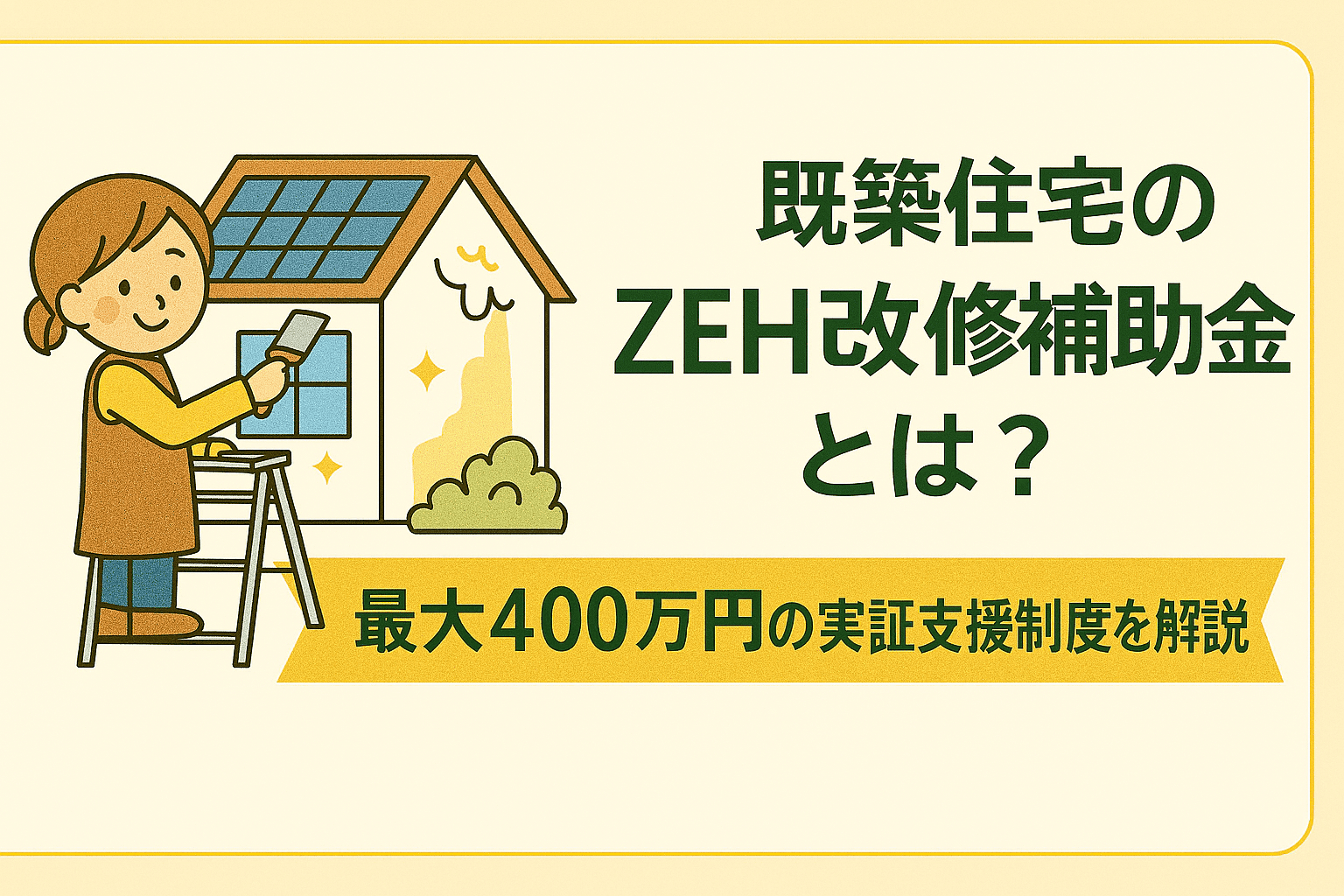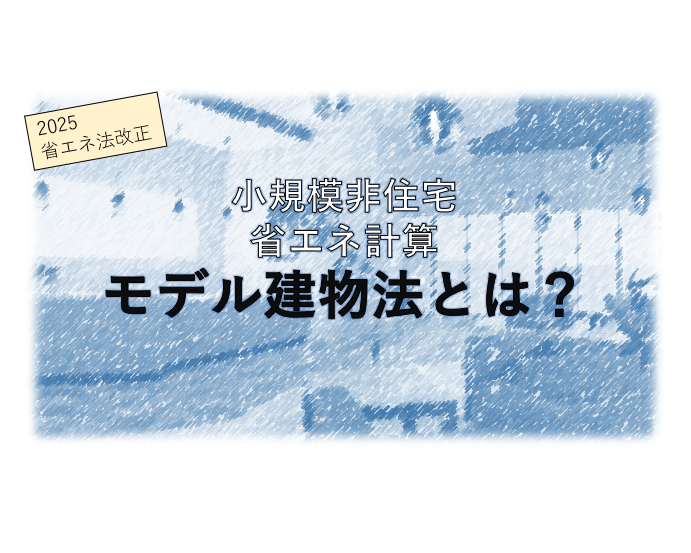COLUMN
お役立ちコラム
2025/10/31
【2025年法改正対応】省エネ適判の審査機関はどこが良い?確認申請と分けるべき?
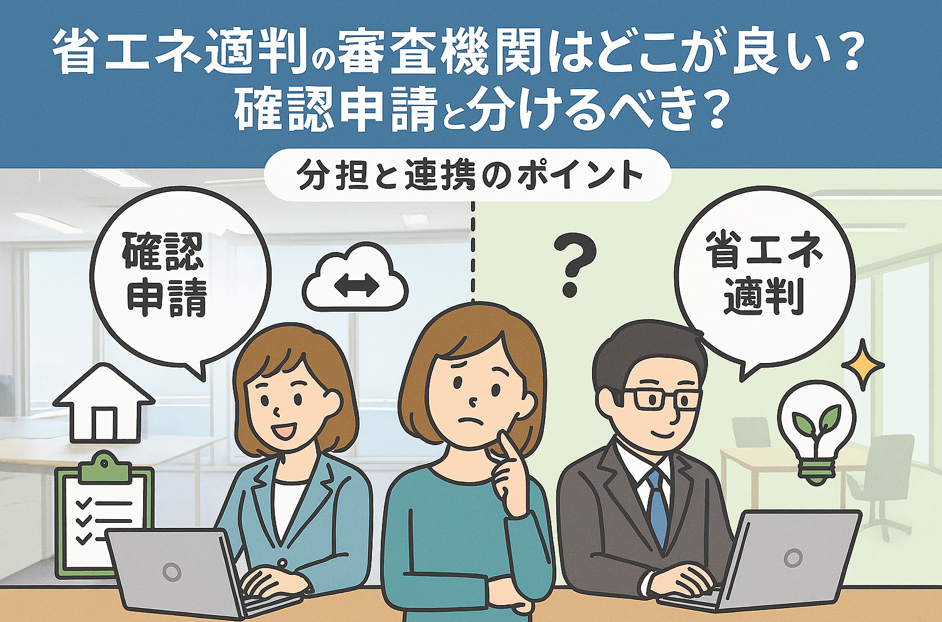
2025年4月より、平屋200㎡以下を除くすべての建築物にて省エネ適判等の対象に。
4号特例縮小もあり、確認申請先の機関が大混雑、省エネの審査が影響を及ぼしているケースも多々出てきました。
省エネ適判の申請先を同一機関が良いのか、どこに出せば良いのか、そのあたりをお伝えしていきます。
省エネ対応をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
- 目次
-
- 1.省エネ適判をどこに申請すべきか
- 1-1.省エネ適判や性能評価に特化した審査機関へ申請がオススメ
- 1-2.確認申請と省エネ適判を分けるケースが出てきている?
- 1-3.審査日数短縮などのメリットあり 増加中
- 2.建築確認と省エネ適判を別機関に申請する場合
- 2-1.申請手数料や完了検査までの日数に注意?
- 2-2.軽微変更の『説明書』『該当証明』により申請先が異なる!
- 2-3.省エネ計算とまとめて外注先に丸投げしてしまうのが楽
- 3.省エネ外注成功のコツ
- 3-1.継続して依頼できる(負担が少ない)外注先と出会う
- 3-2.必要書類送付や、図面追記等の対応はしっかり行う
- 3-3.機械のように作業だけ行う先は避ける
- 4.まとめ
- 4-1.省エネ計算や専門的なことについて知りたい方へ
省エネ適判をどこに申請すべきか
省エネ適判や性能評価に特化した審査機関へ申請がオススメ
確認申請先へ省エネ適判を申請してそこまで支障がない際は、同一機関でまとめるのも手でしょう。
しかし、審査員の業務量増大と、確認・省エネ別担当がそれぞれ順番をかけて見る際の審査時間の増加は避けたいものです。
省エネ適判や性能評価を得意とする審査機関も複数あり、そういった先へ省エネ適判を申請するのがおすすめでしょう。
確認申請と省エネ適判を分けるケースが出てきている?
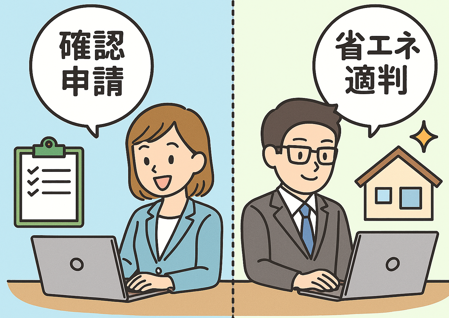
今までは確認申請・省エネ適判を同一機関へ申請することが一般的であり、
国の制度設計のベースともされていたようですが、
法改正後、少しずつ確認と省エネを別機関に申請する動きが増えてきているようです。
さらに、別の機関へ申請することでの弊害がそこまでないことに気づかれ、少しでも早く確認済証交付を目指したい方の選択肢となりつつあるようです。
審査日数短縮などのメリットあり 増加中
省エネや性能に強い機関へ適判申請等を行うことで、審査日数の短縮・柔軟な対応等、メリットが多くあるようです。
確認検査機関の業務量が増え、人手不足が起きている所も出ていることから、省エネ適判を別機関に出すのは理にかなっているように思われます。
効率と品質を両立したいなら、分離申請はとても有力な選択肢です。
建築確認と省エネ適判を別機関に申請する場合
申請手数料や完了検査までの日数に注意?
省エネ適判を別の機関へ出し、確認申請先に適判通知書・副本一式を提出しますと、
確認申請先の手数料が増える(併願割が使えない)、完了検査までの日数が増えるといった懸念が生じるため注意が必要でしょう。
また、確認検査機関にて、審査員と完了検査の検査員が異なる際は、同一機関にて省エネ適判取得の際もそこまで完了検査までの日数等は変わらないのではないかという話もお聞きします。
仕様変更や図面の整合・不整合等も、しっかりそれぞれの申請先への連絡体制を作っておくことが重要でしょう。
軽微変更の『説明書』『該当証明』により申請先が異なる!

法改正までは、省エネ仕様の変更にて特別な手続きを要することはあまりありませんでした。
しかし、省エネ適判等に出している仕様が変わる際は、必ず『軽微変更』の手続きが必要になります。
軽微変更の程度によって対応が変わりますが、別機関に出す際は下記イメージです。
◆軽微変更説明書 ⇒ 確認申請先へ 完了検査申請に提出
◆軽微変更該当証明書⇒ 完了検査までに 省エネ適判先にて申請
◆再適判(省エネ適判先)
軽微変更にはルートA,B,Cといった変更程度がありますので、
詳しく知りたい方は下記コラムもご確認下さい。
※詳しくは審査機関へお尋ねください。
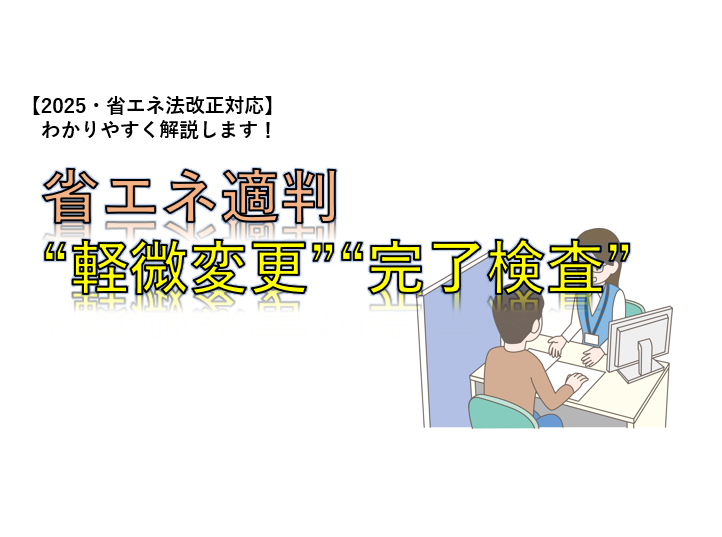
【2025.10月最新】省エネ適判の軽微変更・完了検査についてわかりやすく解説!
戸建・共同住宅等含め対象となります、省エネ適判(省エネ適合性判定)についてのご対応はいかがでしょうか?
適判後の『仕様変更』による軽微変更の対応や、完了検査での対応が非常に厄介になるため、情報を整理しておくことが重要です。
このコラムでは、主に軽微変更ルート(A、B、C)や軽微変更説明書・該当証明書を中心に解説していきます。
省エネ計算とまとめて外注先に丸投げしてしまうのが楽

住宅・非住宅の省エネ計算~適判は、意匠図や省エネ設備との連携を前提として、
外注先へ丸投げしてしまうと効率が良いでしょう。
メールの質疑対応にて、面倒な申請書作成から審査機関への手数料支払い、質疑やり取りまでをやって頂けます。
省エネ外注成功のコツ
継続して依頼できる(負担が少ない)外注先と出会う

毎回申込書に物件名から細かい仕様まで書かされる、返事や対応が遅い、担当者が毎回異なり面倒、といった、
継続的に依頼するには負担が大きすぎる先は避けたほうが良いでしょう。
必要書類送付や、図面追記等の対応はしっかり行う
負担を少なくする≒限りなくお任せする、というわけではありません。
必要書類や確認事項はしっかり対応することと、設計者として図面追記が必要な場合は行うのが前提です。
特に期限が定められている際は、逆算して急ぎ計算、申請しないといけない場合があり、その時は双方が協力できる体制が必要です。
機械のように作業だけ行う先は避ける
決められた申込書等に全て書いていないと着手しない、現場の状況等を理解していない、融通が極端にきかない、といった、
作業は行うが機械のような対応しかできない外注先は避けたほうが良いでしょう。
◆ECOPLUSは地元で計算サポートを進めてきたスタッフが対応します
ECOPLUSですが、サイト立ち上げ前から10年近く、
地元工務店様・設計事務所様への省エネサポートを中心に、少しでも良いお力添えが出来るよう取り組んでまいりました。
お電話とメールにて、顔がなかなか見えない距離かもしれませんが、その隙間を埋められるよう、丁寧に対応させていただきます。
まとめ

法改正後の省エネ適判の申請先・外注成功のコツ等をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
省エネが確認申請や工事に関わることになり、住宅ローンの実行にまで影響が出るようになってしまいました。
少しでも日数短縮するには、別機関への申請も1つとご認識頂けますと幸いです。
お読み頂きまして、ありがとうございました。
省エネ計算や専門的なことについて知りたい方へ
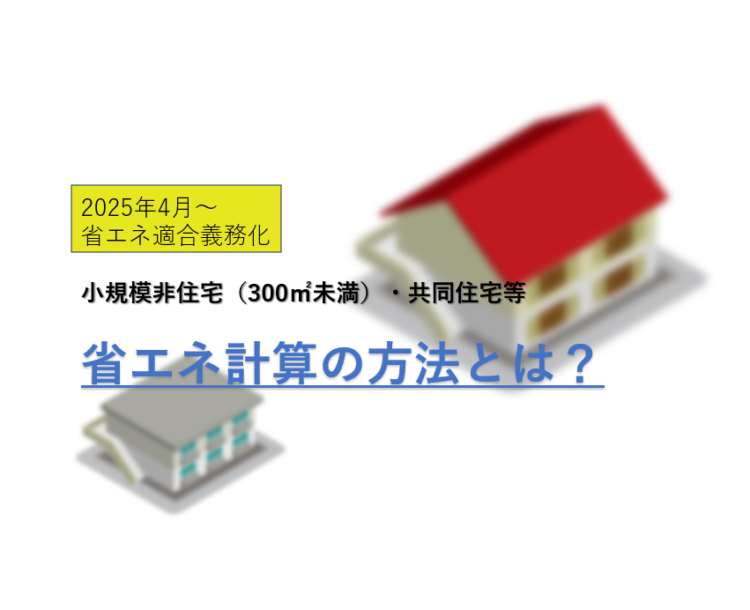
【要確認/省エネ適判】共同住宅や小規模非住宅は仕様基準が可能?省エネ計算のやり方を解説
2025年4月着工の全ての住宅・非住宅が、省エネ基準適合義務となりました。
共同住宅や小規模非住宅も、例外なく省エネ検討・適判の対象になりましたが、ご対応はいかがですか?
仕様基準が使えると思ったらダメだった、そもそも計算方法が違うとは・・・とならないために、注意点や要点をまとめました。