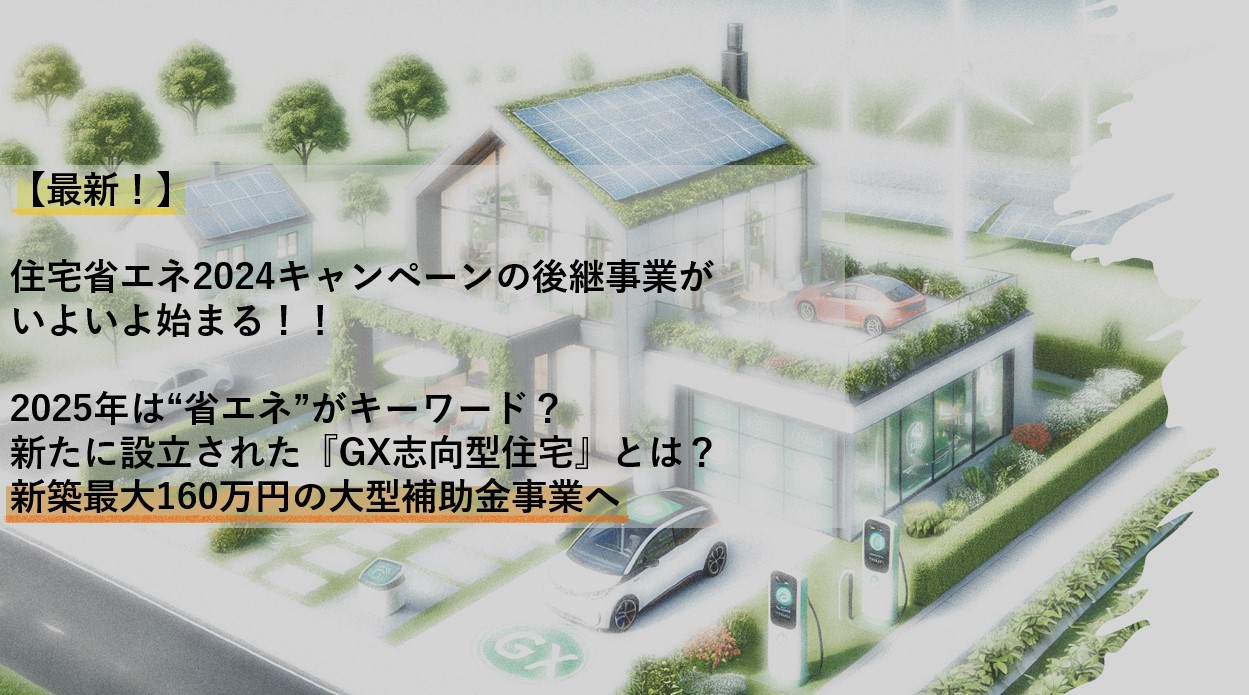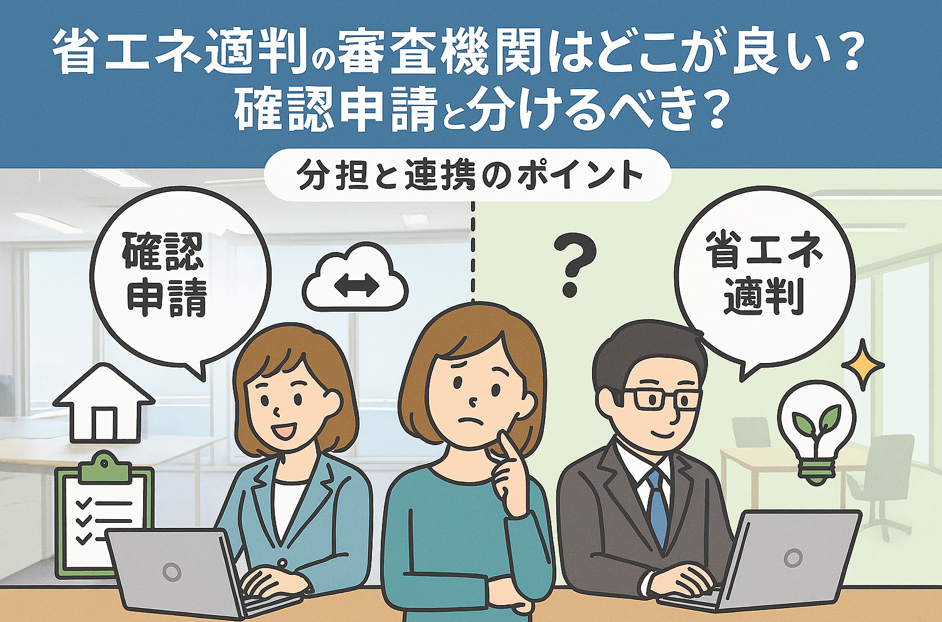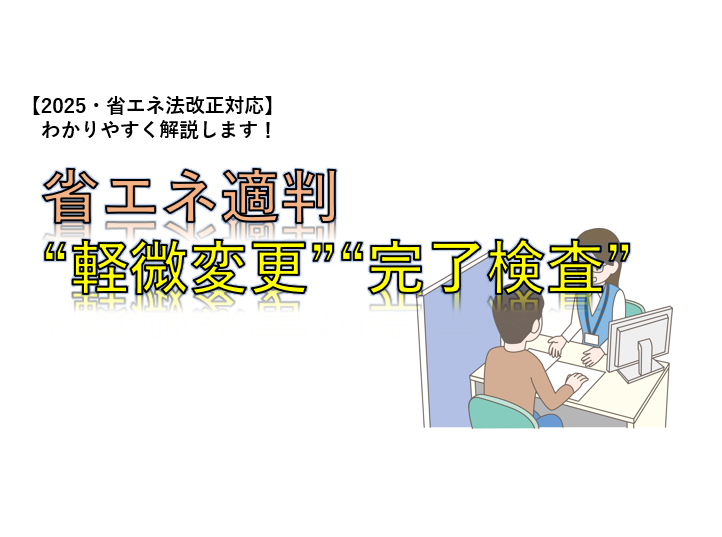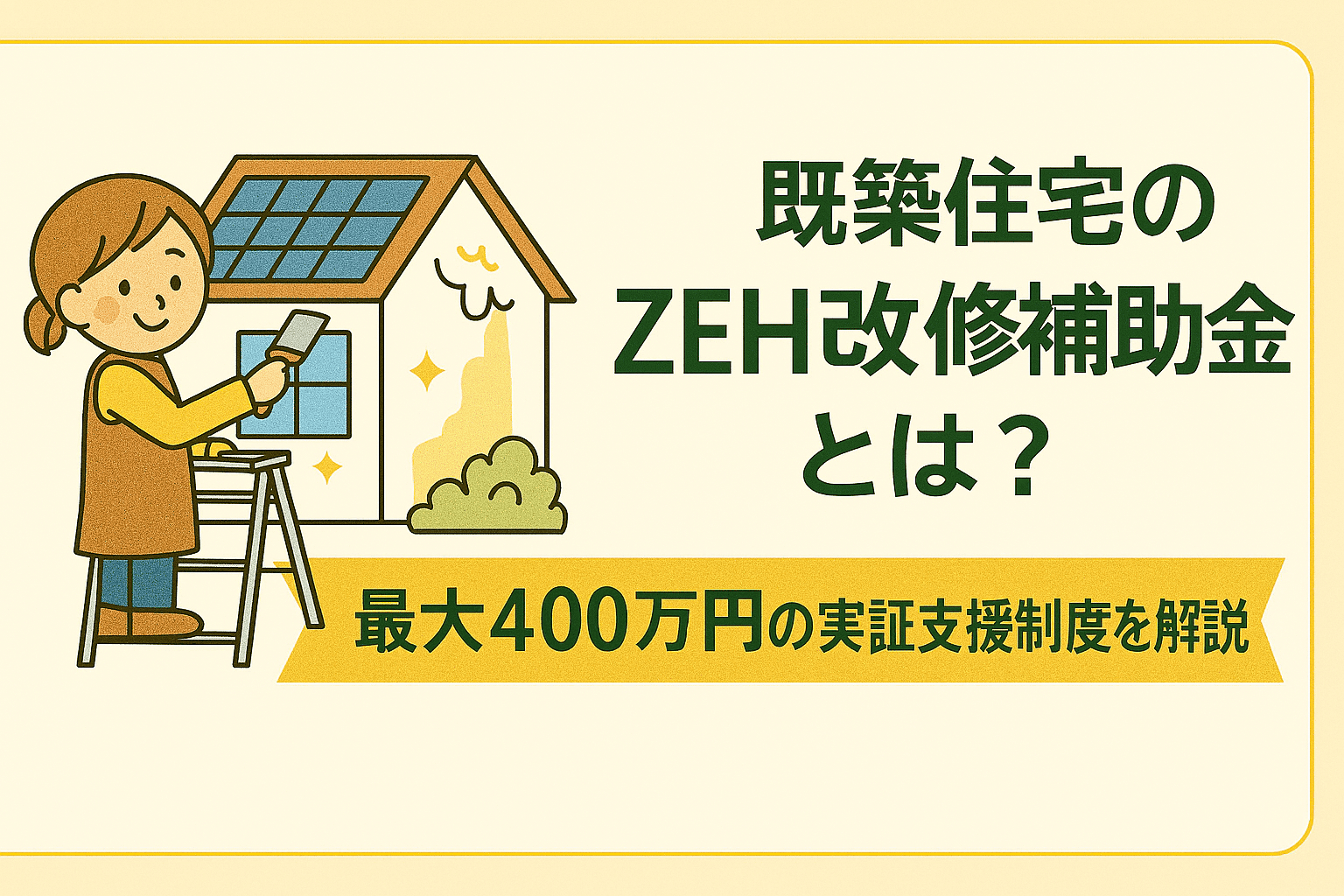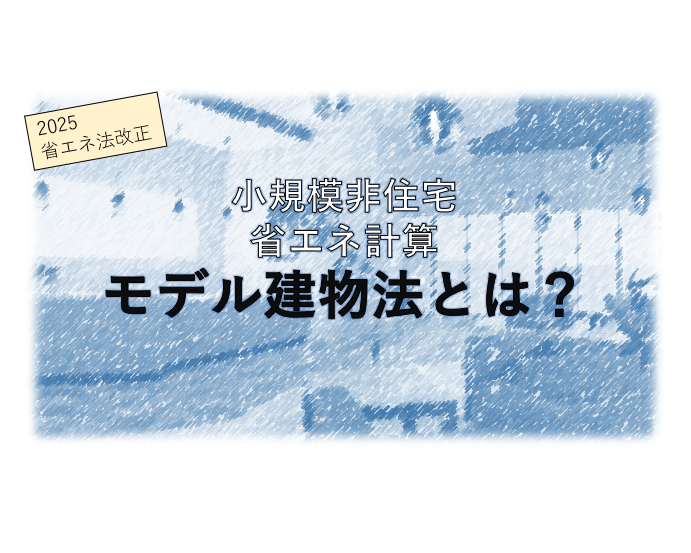COLUMN
お役立ちコラム
2025/08/25
【建築物省エネ法】仕様基準とは?性能基準(計算)との違いについて解説します。

2025年4月に改正建築物省エネ法が施行され、省エネ適合義務化・一部を除き確認申請等への提出が必要となりました。
仕様基準という、今まで聞いたことのある程度だったものが実務にて必要となり、国交省のHPをご覧になってもよくわからないケースが多く出ていると思われます。
そこで、仕様基準がどういったものであり、使える場合と使えない場合等、要点をまとめていきますので、ぜひ参考にして頂けたら幸いです。
- 目次
-
- 1.省エネ検討の仕様基準とは?
- 1-1.住宅用途の場合のみ活用可能
- 1-2.省エネ基準とZEH水準(誘導基準版)の2つがある
- 1-3.RC造やS造(鉄骨造)、共同住宅等も活用可能
- 2.確認申請への提出 HOWTO
- 2-1.提出書類:仕様表→計算書の代わりに
- 2-2.住宅の増改築 『外皮』は仕様基準一択!
- 2-3.店舗併用住宅は?
- 2-4.完了検査への提出
- 3.仕様基準のメリット・デメリット
- 3-1.メリット:確認済証交付までが早い!
- 3-2.デメリット:同じ基準達成のために仕様を上げないといけない
- 4.まとめ
- 4-1.外注先でお困りの方へ
省エネ検討の仕様基準とは?
住宅用途の場合のみ活用可能
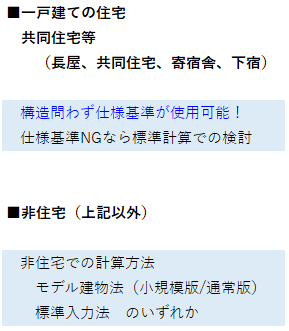
2025年4月より全面的に義務化された、建築物の省エネ基準適合。
適合しているかの確認には、計算によって求める方法と、国が定めた基準に適合しているかを確認する方法の2つがあります。
後者がいわゆる『仕様基準』であり、住宅(マンション、下宿等も含む)のみが使用可能です。
※住宅と似た間取り・構造・規模であっても、確認申請の用途が非住宅である場合は、仕様基準は使えず、
非住宅の計算となります。
省エネ基準とZEH水準(誘導基準版)の2つがある
仕様基準は2つのグレードにて用意されています。
既に義務化された省エネ基準版と、2030年までに義務化予定の『誘導基準(ZEH水準)版』の2つがあります。
いずれも実際に外皮計算・一次エネ計算を行ったより仕様を高めないと基準達成が厳しくなるため、注意が必要です。
※誘導仕様基準を用いてBELS取得を行い、ZEH水準の評価を受けることができます。
RC造やS造(鉄骨造)、共同住宅等も活用可能
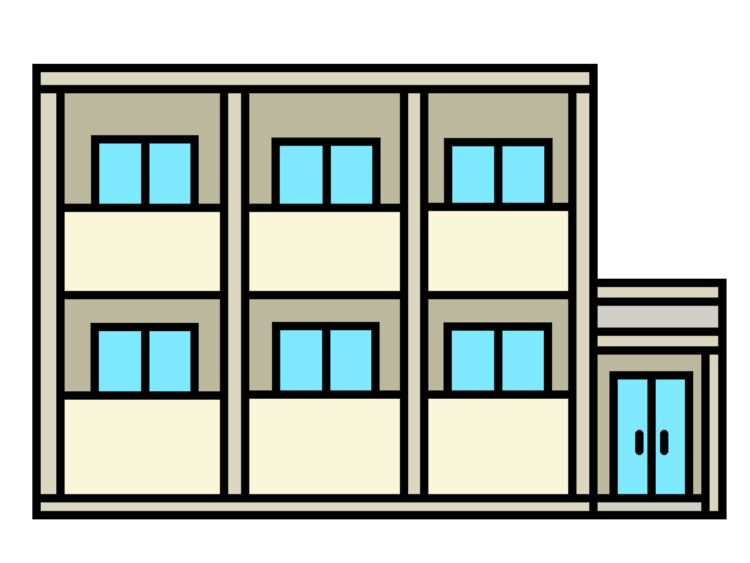
国土交通省の省エネ法のページにて、従来仕様基準ガイドブックなどでは『木造』『RC造(8地域のみ)』のみの記載でしたが、
近年、RC造やS造(鉄骨造)も活用可能と補足が追加されました。
これは、仕様基準が基本的には告示に従って提出するものであり、
わかりづらく全国で混乱があったためではないかと思われます。
なお、共同住宅においては、界壁・界床は基準確認の対象外とされています。
確認申請への提出 HOWTO
提出書類:仕様表→計算書の代わりに
仕様基準は何を提出すれば良いのかわかりづらい一面がありますが、
性能評価やBELS等にてご提出頂いている計算書が仕様表・仕様書に変わるイメージです。
国交省が提示しています『仕様表作成ツール』『チェックリスト』等もお使い頂けますが、
木造戸建とRC造(8地域)以外は未対応の為、エクセルなどで仕様表を作成しなくてはなりません。
仕様基準の基準値と、適合可否も書いておくと良いでしょう。
その他、機器表や仕様を記載した意匠図、設計内容説明書を確認申請等へご提出頂きます。
住宅の増改築 『外皮』は仕様基準一択!
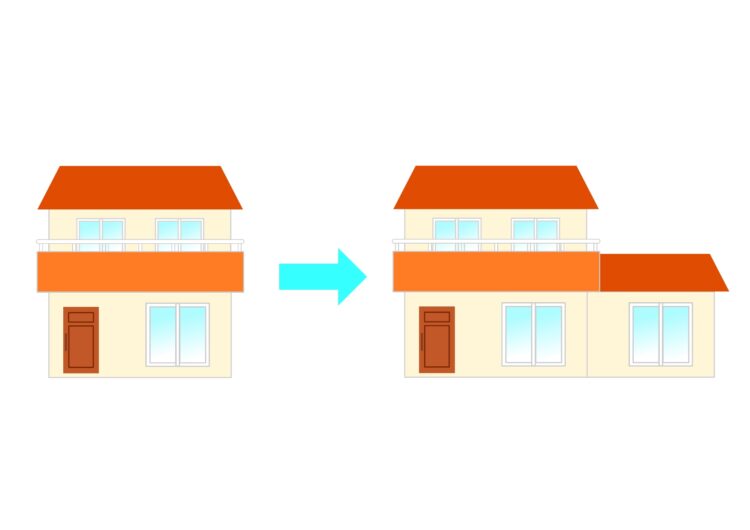
増築や改築の際は、工事を行わない現存部分との境目の検討が難しいことがあり、
住宅での外皮性能評価は『仕様基準』一択となっています。
一次エネルギー消費量性能は、『仕様基準』もしくは、『一次エネルギー消費量計算(外皮性能は仕様基準として選択)』となります。
省エネ適判を避けたい際は、両方とも仕様基準にされることをおすすめします。
なお、設備では増改築部分にて設置されるもののみが基準確認の対象となります。
※非住宅は計算を行わなくてはなりません。
店舗併用住宅は?
難しくはなくとも面倒なのが併用住宅です。
住宅部分は計算あるいは仕様基準での適合確認を行い、非住宅部分は非住宅での計算(モデル建物法等)を行います。
■住宅・非住宅間の建具や間仕切り壁について、計算に困ったことはございませんか?
仕様基準では界壁・界床にあたる部分は対象外ですが、住宅での計算や非住宅では対象となります。
技術情報(※)によりますと、隣接空間に通ずる開口部の熱貫流率が記載されており、
何らかの空気の流れを抑制する部材がある際は熱貫流率4.55、何もない(住宅と事務所間が同一空間の場合等)際は熱貫流率17.0が使えるとされています。
※技術情報 第三章・第三節 3-3-8より
https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_250401_v24.pdf
完了検査への提出
平屋かつ200㎡以下の建築物を除き、
新築・増改築での建築確認の完了検査時に、省エネの検査も行われるようになりました。
仕様基準も当然ながら対象のため、準備しておくことが大切でしょう。
断熱材などの隠ぺい部は特に、写真や納品書等、根拠書類を揃えて建築士による確認をしておくことが重要です。
仕様基準のメリット・デメリット
メリット:確認済証交付までが早い!
省エネ適判の際ですと、外皮計算書や根拠図面、資料などを評価員・検査員の方が見比べて審査を行っていくことになりますが、仕様基準では求積根拠の確認等がないため、相対的に早く確認済証交付を受けることができます。
審査手数料も抑えられる他、適合確認の仕様対象も限られるため、万一仕様変更が生じても影響を抑えられることもメリットといえるでしょう。
デメリット:同じ基準達成のために仕様を上げないといけない

仕様基準では複雑な検討を行わない分、不利側となります。
不利側とは、同じ基準に対して、仕様を相対的に上げないと達成しないということになります。
吹付断熱材等は、ZEH水準達成の厚みでも、省エネ基準の仕様基準がそもそも適合せず、厚みをふかすことが多々見られるため注意が必要でしょう。
まとめ
仕様基準のことについてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
名前は聞いたことがあっても、実務での経験がまだまだ少ない内容と思われます。
エコプラスでも仕様基準の図書作成に携わることが出ていますので、不明点等は、お気軽に問い合わせいただけたら幸いです。
お読みくださいまして、ありがとうございました。
外注先でお困りの方へ

設計申請代行は、WEB外注との相性が非常に良くおすすめです。
どう外注先を見極めればいいか、お困りではないですか?
下記コラムをぜひ参考にしていただけたら幸いです。
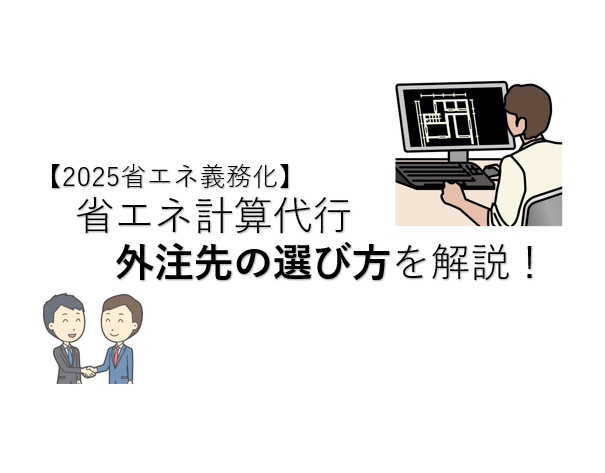
【省エネ適判】 計算・申請代行(共同・非住宅含む)の外注先の選び方とは?目安料金表等も含め解説。
2025年4月より『全ての住宅・非住宅にて省エネ基準適合義務化』スタート。
2階建住宅では、仕様基準や省エネ適判等を行わないといけなくなりました。
確認申請の審査も遅くなり、省エネ適判まで含めて2か月以上かかるという検査機関も出ています。
2025年。省エネ計算から省エネ適判まで、もっと早く出してもらえるところにお願いするのがベストな方法です。
調べてみますと、外注先、申請代行先がたくさんあり、どこに頼んでいいかわからない、とお悩みの方も多いと思います。
ECOPLUSでも外注利用経験がありますので、良い経験・残念だった経験をもとに、選び方のコツを解説します。